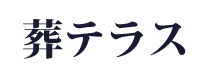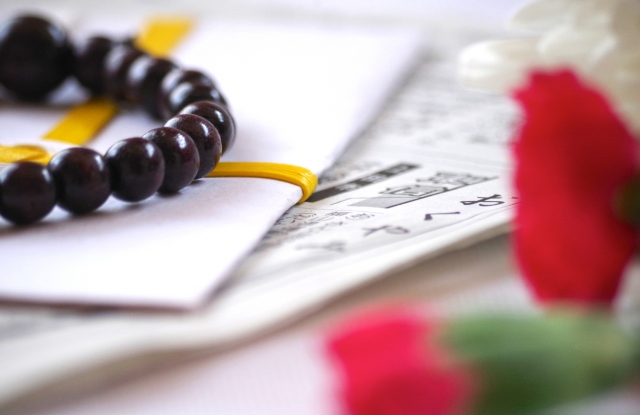忌明けという言葉は聞いたことがあるものの、「そもそも忌明けって何?」「忌明けまでどう過ごせば良いの?」「忌明け後は何をすれば良いの?」と気になったことはありませんか?
忌明けは故人の冥福を祈る大切な期間(忌中)の終わりのことであり、四十九日の法要にて忌明けになります。
あなたが忌明けの意味を知らなくても、世間一般的には忌明けまでは普段より身を慎んだ過ごし方をしなければなりません。神道には「死は穢(けが)れたもの」という考えがあり、他の人に穢(けが)れを広めないために身を慎むということが尊重されているためです。
例えば、忌明け前までは「結婚式などのお祝い事への出席」は避ける必要があり、忌明け後には香典返しなどを送る必要があります。
でも安心してください。お祝い事などに招待されても、事情を説明すれば問題ありませんし、他にも忌明けまでの過ごし方・やってはいけないことを押さえておけば大丈夫。
そのためにも、まずは忌明けはどのようなものか把握することが大切です。
そこで今回の記事では、そもそも忌明けとは具体的にどういった意味なのか?という点から、忌明け前まではやってはいけないこと、忌明け後にやるべきことについて詳しく紹介します。
この記事を読んでいただくことで、「忌明けの本質的な意味」を理解できるだけではなく、忌明け前後の時期を安心して過ごせるようになります。ぜひ最後までお読みください。
目次
全宗派
対応
僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。
365日年中無休です。
事前相談無料
定額のお布施
心付け不要
見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください!
忌明けとは?3つの知っておきたいこと
忌明けとは、「忌中」と呼ばれる期間が終わることです。忌中は普段と違った生活をする必要があるので、3つの知っておきたいことを押さえておきましょう。
1)忌明けまでは慎んだ生活をする必要がある
2)四十九日の法要で忌中が終わる
3)喪中よりも短いが、厳しく身を慎む必要がある
忌明けまでは慎んだ生活をする必要がある
忌中とは親族が亡くなり忌(いみ)に服している期間のことで、忌明けは、故人の忌(いみ)に服している期間の終わりを意味します。
神道では「死は穢(けが)れたもの」であり、他の人にうつると考えられているので、忌中の間は自宅にこもりお祝い事を控えるなど身を慎んだ生活をする必要があります。
忌中が終わっても喪に服す期間(喪中)は終わらないため、控えるべき行動が一部解禁となるのです。
四十九日の法要で忌中が終わる
この忌中の期間は四十九日の法要までとされており、四十九日法要が終わると忌明けとなります。これは、死者の魂の行き先が決まるのが四十九日だからです。
仏教では、忌中の間は忌明け(四十九日)まで、7日ごとに「忌日法要」を行います。忌日法要は次の通りです。
※亡くなった日を1日目としてカウント
・初七日:死後7日目
・二七日:死後14日目
・三七日:死後21日目
・四七日:死後28日目
・五七日:死後35日目
・六七日:死後42日目
・七七日=四十九日:死後49日目
初七日と四十九日は僧侶や近親者、故人の友人を招きますが、それ以外は遺族だけで行うケースがほとんどです。
四十九日の詳しい情報は、「49日を迎える前に知っておきたいマナー・当日の流れなどの全知識」で多くの記事と一緒に掲載しております。合わせてお読みください。
喪中よりも短いが、厳しく身を慎む必要がある
忌中に似ている言葉に「喪中」がありますが、忌中は49日法要が終わるまで、喪中は一周忌までの1年間、と喪に服す期間が違います。
忌中は喪中よりも行動が制限され厳しく身を慎む必要があります。
| 忌中 | 亡くなってから四十九日の法要が終わるまで。死の穢(けが)れを周囲にうつさないために、身を慎んだ生活をする。 |
|---|---|
| 喪中 | 亡くなってから基本的に1年間。故人の死を悼む期間で、一部のお祝い事などを避ける。 |
故人との血縁関係によって喪に服す期間が細かく分かれているので注意してください。
| 故人との血縁関係 | 喪に服す期間 |
|---|---|
| 配偶者、父母 | 12~13ヶ月 |
| 子ども | 3~12ヶ月 |
| 兄弟姉妹 | 3~6ヶ月 |
| 祖父母 | 3~6ヶ月 |
忌明けまでにしてはいけないこと7つ
四十九日の法要が終わり忌明けするまでは、死の穢(けが)れを広めないために自宅にこもって祈りを捧げ、なるべく派手なことは控えます。
ただし、忙しい現代人が自宅にこもるのは現実的ではないため、マナーとして以下の7つの行事を控えておけば大丈夫です。
1)結婚式などの出席
2)神社参り
3)正月のお祝い
4)年賀状を出す
5)お祭りへの参加
6)旅行
7)新居の購入・引越し
1)結婚式などの出席
お祝い事の代表である「結婚式」は、忌明けまでに招待されたときは出席を控えます。先方に事情を説明して欠席を伝えましょう。
忌中は死の穢(けが)れを広めないようにするため、お祝い事などの華やかな場など人が集まる場所への出席は控える必要があります。
2)神社参り
神社は神様がまつられている神聖な聖域とされているため、死の穢(けが)れを持ち込むのはNGとされています。
もし神社にどうしても参拝したい場合は、参拝先の神社に連絡し境内の外でお祓いをして、穢(けが)れを祓ってもらえば大丈夫です。
3)正月のお祝い
新年もおめでたい行事とされており、結婚式同様に正月のお祝いも避ける必要があります。
正月のお祝いや正月飾りなども、神道が由来のものであるため、死の穢(けが)れを他のものから遠ざけると考えられています。
4)年賀状を出す
忌中は喪中期間に含まれているため年賀状を送りません。忌中・喪中期間に新年を迎える場合は、事前に「喪中はがき」を送り知らせます。
喪中はがきであることが分かりやすいように、地味で胡蝶蘭などの花がデザインされているものを使うのが一般的です。また、挨拶などが既に印刷されているハガキは用意する手間が省けるのでオススメです。
【喪中はがき】
5)お祭りへの参加
お祭りは神様を祀るための儀式であるため、神社への参拝と同様に死の穢れがある期間は参加を控えます。
また、神社の参拝と同様に、参加しなければならない事情がある方は神社に説明し、お祓いをしてもらうことで参加できます。
6)旅行
旅行はお祝い事ではないですが、「派手なこと・遊興」に含まるため控えましょう。忌明け後であれば、旅行などに出掛けても問題ありません。
7)新居の購入
新居の購入や引越しも忌中には控えましょう。忌中は故人を供養し最後の別れを惜しむ時期になるためです。
家などの新しいところに移動することは、「お祝い事」「めでたいこと」であると考える方もいるので控えた方が良いでしょう。
全宗派
対応
僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。
365日年中無休です。
事前相談無料
定額のお布施
心付け不要
見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください!
忌明け後に行うこと
忌明け後にはいくつかやるべきことがあります。条件に該当する場合は忘れずに行うようにしましょう。
1)香典返し・忌明けの挨拶状を送る
2)神棚封じを解く
1)香典返し・忌明けの挨拶状を送る
忌明け後は、通夜・葬儀に参列された方に無事に忌明けを迎えたことを報告する意味で、香典返しを挨拶状と一緒に送ります。案内状は奉書紙に書き、品物に添えてください。
忌明けは四十九日の法要後になるため、四十九日法要に参列された方には送る必要はありません。現地でお礼・挨拶と一緒に引き出物を渡しましょう。
香典返し(引き出物)の相場は、香典の金額の半額ほどとされていますが、他の方と差をつけるのは良くないため、一律同じ物を送ります。そのときの相場は2,000円~5,000円前後と考えておくと良いでしょう。
品物は実用的なタオルなどの日用品や日持ちする食品が選ばれることが多いです。
【挨拶状サンプル】
(基本的に縦書きで、句読点は使いません)・頭語+季節の挨拶
例)拝啓 〇〇の候 皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます・通夜・葬儀に参列したことのお礼
例)先般 亡父 〇〇〇〇(故人のフルネーム)葬儀に際しましてはご多忙の中にもかかわらずご会葬を賜り 心より厚くお礼申し上げます・忌明けの報告
例)お蔭をもちまして 〇〇〇〇(戒名)の四十九日法要を滞りなく営み忌明けを迎えることができました・引き出物の案内と文末の挨拶
例)つきましては供養の印に心ばかりの品をお送りいたしますので ご受納いただければ幸いです本来であれば拝眉の上お礼申し上げるべきところですが略儀ながら書中をもちましてお礼のご挨拶とさせていただきます 敬具
・日付
・住所
・施主
2)神棚封じを解く
神棚は神様を祀るための祭壇であるため、死の穢れがある忌中の間は「神棚封じ」を行い、忌明けとともに神棚封じを解きます。
よく忌明けとともに「仏壇の扉を開ける」という話を耳にしますが、仏教では死を穢れと考えていないため、神棚封じと混同してしまったと考えられています。
葬儀屋さんなどからも「忌中は仏壇の扉を閉めておきましょう」と案内されることが多いですが、閉めておく必要はありません。それでも、気になる方は閉じておくと良いでしょう。
忌明け後に行う法要
忌明け後に行う法要は大きく分けて「百箇日法要」と「年忌法要」の2つがあります。法要には親族や故人の友人を招待することもあるため、法要の種類とスケジュールを事前に押さえておきましょう。
百箇日法要
百箇日法要とは、故人が亡くなってから100日目に行う法要で、基本的に自宅の仏前で行います。四十九日法要と比較すると、親族や近親者のみが参加するため比較的こじんまりとした法要です。
小規模な法要であり、僧侶を招いて読経してもらい、お焼香・説法を拝聴して終了になります。その後は、故人を偲んで(しのんで)会食を行います。
年忌法要(一周忌~三十三回忌法要)
百箇日法要の次にある法要は一周忌・三回忌・七回忌などの年忌法要です。法要によっていつ行うのか、年数のカウント方法が異なるので注意しましょう。
スケジュールが不安な方は、葬テラスの『法要の日取り計算表』というツールがあるので利用するのがオススメです。亡くなった日を入力するだけで、次の法要が分かります。
●百箇日法要以降の主な法要
| 一周忌 | 亡くなってちょうど1年目に行う法事。親族だけでなく故人と親しかった友人・知人を招くことが多い。この一周忌で「喪が明ける」とされている。
一周忌に関連する記事 |
|---|---|
| 三回忌 | 2回目の命日に行う法事。親族以外にも故人の友人・知人を招くことが多いとされている。
三回忌に関連する記事 |
| 七回忌 | 満6年目に行う法事。一般的には遺族や親族だけで実施することが多い。
七回忌に関連する記事 |
また、年忌法要は弔い上げとして三十三回忌まで行いますが、宗派によっては五十回忌まで行うので、事前に確認しておくと良いでしょう。
●宗派ごとの法要
| 天台宗 | 初七日~三十三回忌 |
|---|---|
| 真言宗 | 初七日~三十三回忌 ※地域によっては百回忌まで行うことがある |
| 曹洞宗 | 一周忌~五十回忌 |
| 臨済宗 | 初七日~三十三回忌 ※地域によっては百回忌まで行うことがある |
| 浄土宗 | 初七日~三十三回忌 ※地域によっては百回忌まで行うことがある |
| 浄土真宗本願寺派 | 一周忌~五十回忌 |
| 真宗大谷派 | 一周忌~五十回忌 ※地域によっては百回忌まで行うことがある |
| 日蓮宗 | 初七日~三十三回忌 ※地域によっては百回忌まで行うことがある |
まとめ
忌明けとは、故人が亡くなってから四十九日を迎えるまでの「忌中」が終わることです。
忌中はせっかくの結婚式やお祝い事への参加を控えなければならない大変な期間なので、忌明けを無事に迎えれば一安心できるでしょう。ただし、無事に忌明けを迎えても香典返しや挨拶状を送る必要があるので覚えておくことも大切です。
大切なことは「決まったルール」として守るのではなく、なぜ一部の行動を制限して身を慎む必要があるのか理解することです。忌明けの意味が分かれば、故人の供養も適切に行えるでしょう。
忌明け前後は何かとバタバタすることが多いですが、適切な過ごし方を把握しておけば、忌明けまで安心して過ごせます。忌明け後の親戚付き合いなどにも大きく影響します。
今回の記事を参考にして、忌明けまで適切に過ごせるようになることを祈っています。