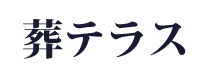人形供養って、ただ不要になった人形を捨てるだけでも利用できるの?髪の伸びる日本人形とかじゃなくても大丈夫?供養なんてして、逆にたたられたりしない?供養に意味なんてあるの?
あなたは人形供養についてどこまでご存知でしょうか?
今まさに、「手放したい人形やぬいぐるみがあるけれど、バチが当たりそうで捨てられない」と悩んでこのページをご覧になっている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回の記事では、人形供養の目的・供養の流れ・費用などわかりやすく全てをご紹介します。
最後まで読めばあなたも不安な気持ちはなくなり、人形に心配ごとなく「さよなら」を伝え、すっきりとお別れができるようになります。ぜひ最後までお読みください。
目次
全宗派
対応
僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。
365日年中無休です。
事前相談無料
定額のお布施
心付け不要
見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください!
1 人形供養とは?
人形供養は、お坊さんに読経してもらうことで「役目を終えた人形に感謝を伝え、魂を人形から抜いて天へ返す」ことができる儀式です。
「後悔しないお別れができる」「けじめをつけれる」「納得して捨てられる」というメリットがあり、何だか捨てにくい…と感じていた思い出のある人形やちょっと気味の悪い人形もすっきり手放すことができます。
供養は必須ではありませんが、お別れの仕方が「テキトー」だったり、捨て方の納得度合いが「微妙・不安が残る」ままだと、あまり良いことがありません。
例えば、後から病気やけがをした時に「もしかしてお人形が怒っているのでは」と思い至る後悔の原因になりますので、やっておくとより良いでしょう。
1-1 人形供養の対象となる「モノ」
人形供養と一口にいっても、対象となるモノは、いわゆる日本人形だけでなく多岐に渡ります。
悩んでいるものがご紹介する中にあれば、安心して人形供養に出せるきっかけにもなるかと思いますので、確認してみてください。

人形供養対象例:
日本人形・ひな人形・五月人形や兜・ぬいぐるみ・おもちゃ・お守り・フランス人形・こけし・ガラスケースなどに入った人形・天神さま・羽子板・だるま・抱き人形・市松人形・ 舞踏人形・博多人形など。
1-2 供養でよくあるシチュエーション
人形供養を頼まれる方に多いシチュエーションを知ると、「自分の人形を供養に出してもいいの?」「出すほどのものなの?」という不安の解決になります。
実際は「役目を終えたひな人形や五月人形」「大切にしていたぬいぐるみ」「ゴミに出すのは気乗りしない」「ずっと子供が遊んでいたものだからちゃんと供養して捨てたい」といった理由がほとんどです。
【1位】
役目を終えた雛人形・五月人形・五月飾り
子どもが遊んでいた人形・おもちゃ・ぬいぐるみ
遺品整理で出てきた人形・ぬいぐるみ
【2位】
壊れた日本人形・フランス人形
貰い物でごみとして捨てるのは抵抗がある
捨てたいが申し訳ない・忍びない
思い出が詰まったものだから可哀そう
【3位】
手作りなので捨てにくい
【4位】
断捨離したいけど捨てた後が怖い
【5位】
髪が伸びるなど怪奇現象がある
人形供養は誰でも利用できる身近な儀式なんです。
ですが、テレビのホラー番組などで、「髪が伸びる人形・涙を流す人形」と、いわくつきの人形に行うイメージが定着してしまったせいで、誤認されている方も多いんです。
感謝を伝え気持ちよく手放したい…そんな気持ちになったら、どなたでも利用可能で、お人形に最も感謝を伝えられる方法でもあるのが、人形供養なのです。
2 人形供養の方法は『自分で供養する』『僧侶に頼んで供養する』の2つ
人形供養には、『自分で供養する』『僧侶に頼んで供養する』の2つの方法がありますが、どちらで行うかはそれぞれの供養の流れや注意点を知ってから決めることが大切です。
それぞれの方法でお人形にしてあげられる供養の「内容」も異なりますので、自分の望む供養ができる方法を選択する必要があるからです。
- 自分で供養する
- 僧侶に頼んで供養する
(1)自分で供養する
人形供養は「お人形を手放す側の気持ちの問題がとても重要」なので、もしあなたが「自分でお礼を伝えるから僧侶の読経は不要」「お金も節約したい」「人形もわかってくれる」と思うなら、自分での供養がオススメです。
メリットとしては、僧侶さんにお願いしないかわりに「費用がかからない」点があげられます。
供養の流れ
準備する物は、『和紙(もしくは白い布)』『お清めの塩』の2つです。
和紙やお清めの塩はスーパーやホームセンターにも売っていますし、次のようにインターネット通販でも購入可能です。
手順
- お人形のホコリや汚れをキレイに落とします。
- 和紙や白い布を用意し、その上に人形を置きます。
- 人形にお清めの塩をまきます。
- お人形を和紙か白い布でくるみます。
- お人形に手を合わせ、「ありがとうございました。」と心から感謝を伝えます。
ここまでで、自分で行う人形供養は終了ですので、最後は『地域のゴミ出しに』出して処分します。
人形供養というと最後は「燃やすもの」というイメージをお持ちの方も多いですが、自分でお人形を焼いてしまうと、『廃掃法』という法律や条例の違反になってしまい、罰せられます。絶対に行わないよう注意しましょう。
自分で行う人形供養のデメリットとしては、「ちゃんと供養できたか?」「自分のやり方で大丈夫だったか?」と不安になってしまうことがある点です。
ご自身はご安心できても、お身内の中には「なんでお坊さんに頼まなかったんだ」とお坊さんの行わない供養に対して否定的な方がいる可能性もあります。
また、供養後は結局ご自身の手で「ゴミ」として処分しなければならないので、「供養はしたけど捨てるとなるとやっぱり後味が悪い」と感じられる方も多くいらっしゃいます。
もしも「自力での供養は自信がない」「身内に反対する人がいる」という場合は、僧侶への依頼も検討してみてください。
(2)僧侶に頼んで供養する
僧侶に頼んで人形供養すると、仏様に最も近いところでお仕えするお坊さんに正しく読経をしてもらえるので、最も確実に感謝を伝えられ、安心してお別れをすることができます。
また、供養後のお人形はお寺でお引き取りしていただけ、寺院によってはお焚き上げ(焼却)まで行ってもらえるので、非常に助かります。
供養の流れ
供養には大きくわけて『合同供養』と『個別供養』の2つがあり、それぞれで供養の流れが異なります。
いずれもお坊さんに寺院などで丁寧に読経していただけ、お人形の魂を天へお返しすることができますが、人によっては一方の供養方法を好まない、と思われる方もいらっしゃいますので、それぞれについて簡単にご説明します。
合同供養

合同供養とは、人形供養を希望する方のお人形が一定量集まった時・寺院で設定している人形供養日までに集まったお人形をまとめて、ご供養する方法です。
| メリット |
|
| デメリット |
|
個別供養

個別供養は、依頼したあなたのお人形に対し、お坊さんが一対一で、あなたのお人形のためだけに読経をあげ、供養を行ってくれる方法です。
| メリット |
|
| デメリット |
|
お坊さんの読経は、あなたの感謝の気持ちを確実にお人形へ届けてくれるものであり、人形に宿っている魂や命・心もキレイに人形から取り払ってもらえます。
ご自身でするよりも安心感がありますし、お身内のかたも「お坊さんがやってくれたなら」とご納得してもらいやすい方法といえます。
供養後の処理もお焚き上げ・処分とお寺によって方法は異なりますが、あなたの手で最後の処分をする必要がなくなりますので、ずいぶんと気持ち的にも楽にお別れができます。
全宗派
対応
僧籍簿登録された僧侶様のみご紹介します。
365日年中無休です。
事前相談無料
定額のお布施
心付け不要
見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください!
3 お坊さんに頼むなら!事前に知っておくべき3つ知識
もし「お坊さんに頼もう」と思われたなら、事前にこれからご紹介する3つの知識を身に付けておくことが非常に重要です。
実は、「お寺に頼めばどこでもどのお坊さんでも一緒だろう」と思っていると、後で大きな後悔をすることになりかねないからです。
- 依頼先の見つけ方
- 僧籍簿を持たない単立宗教法人の寺院や悪質な僧侶の存在
- 依頼先について調べておいた方が良い3つのこと
1つずつ説明します。
3-1 依頼先の見つけ方

人形供養の依頼先には、檀家に入っているなら『菩提寺(ぼだいじ)』、近くに信頼できる寺院があるならその『寺院』へ相談、懇意にしているお寺が無い場合は『僧侶派遣サービス』がオススメです。
祭典ホールのイベントなどで、「無料合同供養祭!」と銘打って定期的に無料で合同供養していることもあります。
「費用も無料だし…」と利用を検討する場合は「どんな寺院のどんな僧侶が供養に対応するのか」「供養後のお人形はどのように処理されるのか」を確認しておく方がよいでしょう。
「もう役目を終えたので供養後はお焚き上げしてもらい、ゆっくり休んでもらおう」と思っているのに、供養後に孤児院や幼稚園などに勝手に寄贈されている例もありますので、確認が大切です。
3-2 僧籍簿を持たない単立宗教法人の寺院や悪質な僧侶の存在
意外と知られていないのが、『僧籍簿を持たない僧侶が運営する単立宗教法人の寺院』や『悪質な僧侶』の存在です。
お坊さんの中にも段階があり、一人前の僧侶になって初めて、僧侶としての名前である『僧名(そうみょう)』が与えられ、僧籍簿という僧帳に登録してもらうことができます。
僧籍簿に名前のないお坊さんはまだ半人前であり、僧侶とは呼べません。僧籍簿を持つことで初めて、宗派の中でお坊さんとして認められるのです。
お坊さん・お寺に任せれば何もかも安心、であれば1番ですが、実際はそういった一般的な考えを利用して悪徳なことをしている人や、僧侶として一人前になっていないまま僧侶を名乗る人もいる現実があるのです。
僧籍簿を持たない僧侶が運営する単立宗教法人の寺院

僧籍簿を持たない僧侶の読経では、「寺院にしっかりとした人形供養をしてもらいたい」というあなたの望みは叶いません。
僧籍簿に名の無い段階では僧侶とは言えないので、読経者は僧侶ではなく、あなたが自分で人形供養するのと、何ら変わらない・もしくは気持ちのこもっていない分それ以下の対応になってしまうからです。
単立宗教法人が悪いというわけでは決してありませんが、包括宗教法人・被包括宗教法人と違い、単立宗教法人は適切な儀式が執り行われているか、監視される立場にありません。
自由な運営ができてしまうため、利益のためだけに寺院を運営し、寺院を頼ってきた人に対して酷い対応をする悪質なケースもあります。
近くのお寺さんに頼む時には、「僧籍簿に登録されたお坊さんはいらっしゃいますか?」と確認してみましょう。
僧籍簿自体を見せてもらえるわけではありませんが、明確な答えは返ってきますから、依頼先を決めるうえで、重要な情報になります。
悪質な僧侶
「供養する」と引き取って、勝手にリサイクルショップに売却され、後日店で供養に出したはずの人形を見つけてしまった、という人もいるほどです。
人形供養を依頼する人の多くが、「人形に感謝を伝え、気持ちよくお別れしたい」と感じている中、その気持ちを利用して供養代だけ徴収し、悪質な対応をする存在もいることには、注意が必要です。
3-3 依頼先について調べておいた方が良い3つのこと
良い依頼先を見つかったら、自分が希望する人形供養が行われるかについて確認しておくことが大切です。
寺院によって人形供養の流れも方法も対応も様々ですので、「供養証明書はもらえるのか?」「すぐ供養してもらえるのか?」「本体以外も引き取りしてもらえるか?」は、確認しておくだけで後々のトラブルを回避することもできます。
- 供養が終わったあと「供養証明書」を発行するか
- 供養は随時行われるのか?年に数回だけか
- 人形本体以外も引き取ってもらえるか
1つずつ説明します。
確認点(1)供養が終わったあと「供養証明書」を発行するか
人形供養当日現地に行くことができない場合や、合同供養なのでまだ供養日が確定していない、という時は特に『供養証明書』を発行してくれるのか確認することが重要です。
いつ供養されたのか?を知らないまま、人形を預けて何の連絡もないままでは、気持ちも晴れませんし、気がかりです。
「〇日にお預かりしていたお人形の供養が終わりました。」と一報もらえるだけでも不安は和らぎますが、家族の誰もが安心できるよう、「供養が完了したことを証明する供養証明書」を郵送してもらえるのが1番です。
人形供養の申し込み前に、「人形供養をお願いしたいと思っているのですが、貴院では供養後に供養の完了を証明する供養証明書などは発行していただけるでしょうか?」と聞いてみましょう。
確認点(2)供養は随時行われるのか?年に数回だけか
合同供養の場合でも、供養の時期の確認は大切です。
寺院によっては、年に1~2回決まった日にちのみで供養を行い、それまでは人形を倉庫などで保管するというケースもありますので、いつまでも供養ができないとあなたの気持ちも落ち着きません。
場合によっては、いわくつきのお人形と長期間一緒に保管されてしまう可能性もあるので、最良の供養のために預けたはずのお人形に悲しい思いをさせることになってしまいます。
供養が随時行われるのか、年に決まった日だけにしか行われないのか、預けた日からどれくらいで供養してもらえるのかは必ず確認しましょう。
確認する時は、「貴院では、今回お人形の供養をお願いしますと、いつ頃に供養して頂けるのでしょうか?目安でもいいので時期を教えていただけますか?」と聞いてみましょう。
あまりにも供養が先になってしまう場合は、預けた人形が供養されない状態で何カ月も寺のどこかで保管されることになってしまいますので、早めに供養してもらえるお寺を探すなどよく検討したほうがいいでしょう。
多くの寺院で「人形供養のためにお預かりした人形は、どんな理由があってもお返しできません」と、注意書きがあります。預けてしまってから、「やっぱり辞めた」はできませんので、よく考え最終決断をしてからお人形を寺院に渡すようにしましょう。
確認点(3)人形本体以外も引き取ってもらえるか
人形供養で最も多いのが「ひな人形・五月人形・五月飾り」など、ガラスケースに入ったお人形ですが、寺院によっては、ひな段やガラスケースは受付してくれないことがあります。
人形と一緒に供養してもらい、その後の処理も同時に任せられれば効率的ですし、安心できます。
自分で人形本体以外の飾りやケースなどの処分が難しそう…と感じる場合は、供養を依頼する予定の寺院に、「貴院では人形本体以外の引き取りもお願いできますか?」と確認してみましょう。
お焚き上げとは、供養お祓いの済んだお人形を、寺院内で燃やして浄火することを言います。
廃棄法により一般家庭では、野焼きにあたる行為は法律条例違反になり禁止されていますが、寺院などで行われる宗教行事は例外として認められています。
ですが、最近では人形を燃やすことで健康に害を与えるダイオキシンの発生があることや、近隣住民の気持ちに配慮し、寺院でもお焚き上げは控えるというところが増えています、
昔からの風習で、「お焚き上げが当然」と思って依頼先を探すと、「なかなか寺が見つからない」「どんどん供養が遅れる」と良いことがありません。
供養お祓いが済んだ時点で、お人形の魂はすでに人形から離れ天へ返すことができますので、お焚き上げに関してはあまり重要視せず、供養を最優先に考えることの方が大切です。
4 人形供養にかかる費用の相場
人形供養にかかる費用の相場は、寺院に直接依頼する場合、合同供養で『みかん箱1箱あたり5,000~10,000円』、個別供養の場合、『読経料30,000円前後』です。
僧侶派遣サービスに依頼する場合は、合同供養の場合は『5,000円前後』、個別供養の場合は『30,000円~35,000円』です。
| 寺院 | 合同供養:5,000円~10,000円 ※みかん箱1箱あたり 個別供養:30,000円前後 ※人形本体以外の受付は基本的にしていない |
| 僧侶派遣サービス | 合同供養:5,000円 個別供養:30,000円~35,000円 ※人形本体以外の受付も可能 ※6寺院、僧侶派遣サービス5社の情報をもとに平均を算出しています。 |
5 近所に安心して任せられるお寺がない!そんな時は僧侶派遣サービスへ
お寺さんが見つからない・どこがいいか分からない時は、僧侶派遣サービスの利用がオススメです。
僧侶派遣サービスは、あなたの希望する宗派・日時で対応できるお坊さんを探し、複雑な日程調整などの手配もすべて行ってくれます。
葬テラスでは、人形供養の場合、『訪問供養』『持ち込み供養』『郵送供養』の3つの方法で柔軟にご対応しております。
「お気持ち…」と言われて不安になってしまう料金も、明確な金額が決まっているので悩むことがありませんし、ご希望日で対応できる「僧籍簿に登録のある僧侶」を手配するので、安心です。
悩まれたら1度お問合せくださいね。
まとめ
人形供養は、長い間あなたのそばに居てくれたお人形に感謝を伝え、お人形に宿った魂を天にお返しする儀式です。
自分で行うこともできますし、僧侶に依頼すれば、読経とお祓い、場合によってはお焚き上げで、最良の供養を行うことができます。
依頼先は、檀家なら菩提寺、それ以外なら僧侶派遣サービスを活用すると便利です。
大切な人形とのお別れに、気がかりが残らないよう、しっかりけじめをつけて、すっきり人形を手放せると、後悔もありません。
この記事が、人形供養についてわからず悩むあなたの役に立てば幸いです。